昨日、『創』が主催した映画「ザ・コーヴ」の上映会とシンポジウムに行ってきた。
- 映画「ザ・コーヴ」オフィシャルサイト(http://thecove-2010.com/
)
- 映画「ザ・コーヴ」6月9日上映&シンポへ向けて『創』6月号記事を公開しました。- 月刊「創」ブログ(http://www.tsukuru.co.jp/tsukuru_blog/2010/06/post-120.html
)
「ザ・コーヴ」はイルカビジネスの現状と、和歌山県太地町(たいじちょう)で行われているイルカ漁を描いたドキュメンタリー映画で、「反日映画」であるとして上映中止を求める運動が行われたりしている。映画館に上映中止を求める電話がたくさんかかってきたりしたそうで、東京ではとうとう、公開する映画館がなくなってしまった。「ザ・コーヴ」について語るには、なにはともあれ観てみないといけない。
映画に主役として出てくるのは、かつての人気ドラマ「わんぱくフリッパー」でのイルカの調教師であり出演者だったリック・オバリー。番組がきっかけで水族館ではイルカショーがさかんになったが、胃潰瘍になるため胃薬を飲ませなくてはいけないなどイルカにストレスを強いていることに気がつき考えを改め、今はイルカの解放運動をしている。
そんな中、太地町はイルカ漁でたくさんのイルカを入り江(コーヴ)へ追いつめ、水族館に卸す以外のイルカは全部殺してイルカ肉として出荷していると知り、そのことを告発するべく動いている、といった内容。
うーん、この撮り方、この編集では、太地町の人が怒るのは無理もないと思った。彼らは生活のために、合法的にイルカを捕っている。太地町のイルカ漁はイルカビジネスの現場ではあるけれど、単に現場でしかないともいえる。そこへ乗り込んでいって「やめろー」とかされても、現地の人は困るだけだ。イルカの代金をそっくり補償するからイルカ漁をやめてほしいという申し入れが断られた、といったくだりがあり、これはなかなか象徴的だと思う。すでにお金の問題を通りすぎて、感情的な問題になってしまっている。入り江で隠すようにしてイルカを殺しているのも、活動家たちがやってきてうるさいからではないか、つまり映画は、自分の主張を通すために、原因と結果をわざと取り違えているように感じた。
そのあたりも含めて、映画は太地町の人たちとコミュニケーションをとっていない。リック・オバリーはすでに太地町からマークされているから、彼を中心にしてドキュメンタリーを撮るとなるとこうなってしまうのかもしれない。でもカメラに向かって「帰れ! 帰れよ!」と(日本語で)すごんでいた若い人と、きちんと関係をもってインタビューのひとつもできれば、映画としての説得力はむしろ増すのではないか。
で、それはそれとして、日本での公開にあたってもちょっとどうなんだというところがある。
映画の終わりに、テロップが出てくる。
「劇中イルカの残留水銀が2000ppmとされますが、調査によってばらつきがあります」
「イルカの肉が鯨肉に偽装して出荷されているのではないかという指摘には、太地町や政府からそういった事実はないという反論が出ています」
これらは日本の配給会社が独自に追加したものであることが、上映後のシンポジウムでわかった。うーむ、確かにそれは映画を観て知りたくなったことではあったから、調べる必要がなくなってよかったんだけれど、よかったよかったですむことでもない気がする。
それから、映画に出てくる日本人の顔がほぼ全員ぼかしになっているのも、かえってやりすぎ感があった。
といったあたりはシンポジウムでも出てきた。のだけれど時間が押していて、それぞれが思うことを話しただけで終わってしまった。
補足のテロップやぼかしについては、配給会社のアンプラグドの人が「日本で公開するためにできるだけのことをした結果」と話していた。一方で、こういう自主規制がろくなことにならないという話も出てきた。
会場にはリック・オバリーも来ていた。壇上で「多くの日本の皆さんに映画を観てもらいたくて日本に来た。娯楽作品としてでもいいのでぜひ観てほしい。日本国憲法の21条には表現の自由がうたわれている。その通りになることを願っている」といった話をした。
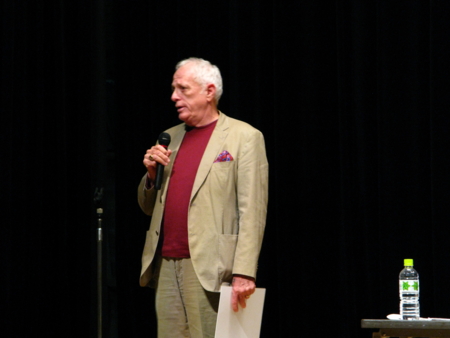
以下、登壇者のひとことを、メモから再現。(念のため、わたしが聞き違い、勘違いしている可能性があります)
森達也(映画監督・作家)
憲法21条でいう表現の自由はもともと、国家が国民の権利を侵害しないように定めたもの。今回のように、国民どうしで表現の自由を認めるかどうかといった議論は想定していない。表現の自由をいうのは大切だが、暴力を付随させるのは間違っている、なぜ今さら表現の自由について議論をしなければならないのか、情けないことだ。
アメリカではマイケル・ムーアの映画も「アバター」も、「アバター」は反米映画であり、作品について活発な議論がなされている。少なくとも上映中止といった話にはならない。
綿井健陽(映像ジャーナリスト)
イルカ漁をやめさせるのに太地町の人に抗議する手法は理解を得られないのでは。彼らは生活をしている。そのことをふまえた上で議論をすべき。リック・オバリーさんは先ほど「娯楽ででも観てほしい」と言っていたが、そうとらえるのは難しい。
この映画で太地町に取材に来る人がさらに増えた。彼らは不偏不党、中立な立場で取材をするというが「中立アレルギー」になっていないか。ドキュメンタリーはそもそも偏っているもの。
坂野正人(映像ジャーナリスト)
「ザ・コーヴ」の上映中止運動のきっかけとして、立教大学での一件があるのではないか。立教で上映会を企画したら、太地町の弁護士から内容証明が届いた。映画に撮られた人の肖像権が侵害されている、また事実誤認があるといった指摘だった。それをうけて大学は、事実確認もせず総長判断で上映をやめてしまった。こういった自主規制、事なかれ主義がこの映画をめぐるキーワードになるのではないか。
もともとドキュメンタリーのモザイクは嫌いなのだがこの映画はモザイクだらけ。配給会社が自主規制をしすぎ。警官の顔にすらモザイクをかけるなど初めて見た。なんとか上映したいという気持ちもわかるがいただけない。

鈴木邦男(一水会顧問)
上映中止が相次ぐのは、映画「靖国 YASUKUNI」の体験があるのだろう。モザイクが多いと、かえっておどろおどろしく感じられた。オバリーさんの反省が出発点になっていることやイルカショーの実態など、興味深い内容ではあった。
議論は映画を観た上で堂々とするべき。見せないようにしてしまうのは間違っている。「反日だ」という抗議はかつて自分もよくやっていたが、(会場、笑)こういうのは自分の基準で仕分けている。反日と決めつけて見せないのは国民をバカにしていて、それはむしろ反日的行動なのではないか。上映反対の人も壇上に呼べばよかった。映画を観た上で、言論で戦えばよい。議論はもっとオープンにするべき。反日というので緊張して見たが、ここまでやればお見事な内容。これを契機に論じ合える場を作ってほしい。
野中章弘(アジアプレス・インターナショナル代表)
表現や言論の自由をうたっていることが民主社会の基本だ。それは憲法21条があるから保証されているのではなく、多くのジャーナリストがかちとってきたもの。なのに日本のジャーナリズムに根づいていない。
自主規制と倫理についての議論がなされていない。日本人のメンタリティでは、集団の中で個を埋没させ、レッテルを貼って情緒に流れていってしまう。日本の病んでいるゆがみについて、もっと議論していきたい。

司会:篠田博之(月刊『創』編集長)
憲法21条について外国の人に言われるのは情けない。自主規制というのは大きな問題で、自分で規制してしまうから文句を言う先がない。映画館だけを責めるべきではない。他人事のように報じているマスコミも問題だ。「表現の自由は認められない」という上映反対派の主張は問題。抗議の自由は認められるべきだが、実力行使で上映を認めないのはどうなのか。
映画「靖国」のときと同じ構造で、またこれかと思う。
今回、客席の前2列を報道席にしてマスコミの皆さんに座ってもらったのは、実力で壇上に上がろうとする人がもしいたら防波堤になってほしいからというのもある。(会場、笑)そのくらいの危機感を持っていつも仕事をしてほしい。
- 坂野
- イルカ漁は合法なのに漁師たちの顔にぼかしを入れている。インタビューされている水産庁の職員にぼかしを入れないのはなぜか。
- アンプラグドの担当者
- 私服警官にぼかしを入れていることについて、その映像がまさに隠し撮りであること、私服なので本当に警官かどうか区別できないためにそうした。また水産庁の職員は公人であるという判断からぼかしを入れていない。
- 綿井
- 太地町へ実際に行ってみるとわかることがたくさんある。皆さんもぜひ行ってみてほしい。自分も太地町へ行き、イルカをなでて、イルカを食べてきた。
- 坂野
- 屠殺現場をわざわざ見せるようなことをするのか、という議論があるがそれは間違い。イルカ漁は野生動物のハンティングであって事情が違う。なのにイルカ漁が水産庁の管轄であるのは本来おかしい。水銀の規制値について水産庁は「イルカは魚ではないので基準を適用しない」という見解。これもおかしい。
- 鈴木
- 映画館は立場が弱い、守る方法はないだろうか。
- 綿井
- 鈴木さんが映画館の入口に立っていれば、これはだいぶ心強いのでは。(会場、笑)
- 森
劇場は宣伝ミスをしている。劇場の選定ミス。「靖国」と同じ映画館で上映しようとしている。それでは問題にされるのも当たり前。ポレポレ東中野やイメージフォーラムで上映すればロングランになったりするのでは。(上映中止しそうな劇場を選んで、宣伝効果を)狙ってやっているように思える。そのうちにイメージフォーラムやポレポレ東中野で上映して大ヒットするのだろう。
まとめ(篠田)
70年代からこういうドキュメンタリーを撮っている人はずっと自主上映でやってきた。映画館を応援してほしい。電話だと向こうは上映してほしいのか上映中止してほしいのかすぐにわからないのでFAXなどで。
編集部にも電話がかかってくることがあるが、相手の主張がすぐにわからないこともある。上映には賛成だが内容には反対、という人もいる。
今日、上映中止を求める団体の人がここへ来たのは偉いと思う。だってものすごくアウェーでしょう。
ただ今日も、表現の自由についての議論にとどまってしまい、作品について議論にすら入れないのはとてもよくなかった。
会場の皆さん、実際映画を観てみて、思っていたのと違ったという人はどのくらいいますか。(多数の手が上がる)これはやはり、実際に見ることが大切だということになる。
シンポジウムの感想とまとめ
篠田編集長が言っていたように、上映中止運動などがあったため表現の自由を再確認する手続きが増えてしまい、そのぶん捕鯨問題なども含めて内容についての議論を深められなかったのはもったいない。
ドキュメンタリーの手法として、また作品としてどうなのかというと、ちょっと一方的、一面的にすぎるように感じる。また上に書いたように、太地町を中心に描くのはセンセーショナルにはなるけれど、運動を完遂するための手としてはあまりよくないとも思った。
あと映画そのものは太地町だけでなく、IWC(国際捕鯨委員会)での日本の話なんかも出てきてなかなか興味深い。気になった人はぜひ機会を見つけて観てみてほしい。
参考記事
上映中止を求める団体のデモについての記事。演説をそのまま書き起こしているのは、そうすることで団体のことをよく理解できると考えたからだろう。また右手を掲げて「ハイル!」と揶揄した相手への暴言にも、団体の本質が透けて見える。
- 渋谷駅にて『ザ・コーヴ』の上映中止を求めるデモが行われる(http://cinema-magazine.com/news/2102
)
「捕鯨は日本の文化」について、そういう言い方は比較的最近出てきたものだと指摘する記事(最後の段落を参照)。そもそも日本人でも、鯨を食べたことがある、鯨を食べたいと思う人はもう少ない気がする。捕鯨問題はなかなか複雑そうで、自分には簡単に結論は出せないけれど。
- 東京大学 新環境エネルギー科学創成特別部門: 目からウロコ?の捕鯨問題(http://ut-ecoene-blog.blogspot.com/2009/10/iwc-iwc-iwc-iwc43-88iwc-43.html
)
捕鯨問題を追っている方のTwitterまとめ。太地町の話も出てくる。
- Togetter - まとめ「捕鯨って、本当に「日本の伝統文化」なの?」(http://togetter.com/li/9780
)
関連書籍
自主規制の問題を鋭く追及する本。面白いです。

- 作者:森 達也
- 発売日: 2003/06/06
- メディア: 文庫
映画「靖国 YASUKUNI」をめぐる議論をまとめた本。会場で販売されていたので買った。
11日追記:記事と動画
当日の様子を伝える記事としてはかなり詳しい。
- 『ザ・コーヴ』東京でイベント上映決行!日の丸掲げ抗議する人も!満席で観客あふれる - シネマトゥデイ(http://www.cinematoday.jp/page/N0024920
)
シンポジウムは全編動画が上がっていた。「映画『ザ・コーヴ』上映中止に反対する!」緊急アピールもここに載っている。
- 映画「ザ・コーヴ」〜上映中止へ抗議のシンポジウム・前編(26分) | OurPlanet-TV:特定非営利活動法人 アワープラネット・ティービー(http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/541
)
- 映画「ザ・コーヴ」〜上映中止反対シンポジウム(後編・16分) | OurPlanet-TV:特定非営利活動法人 アワープラネット・ティービー(http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/542
)
追記:約1年後、NHKスペシャルでも太地町の話が放送されました
- NHKスペシャル「クジラと生きる」のディスコミュニケーション - Imamuraの日記(d:id:Imamura:20110526:whale
)


